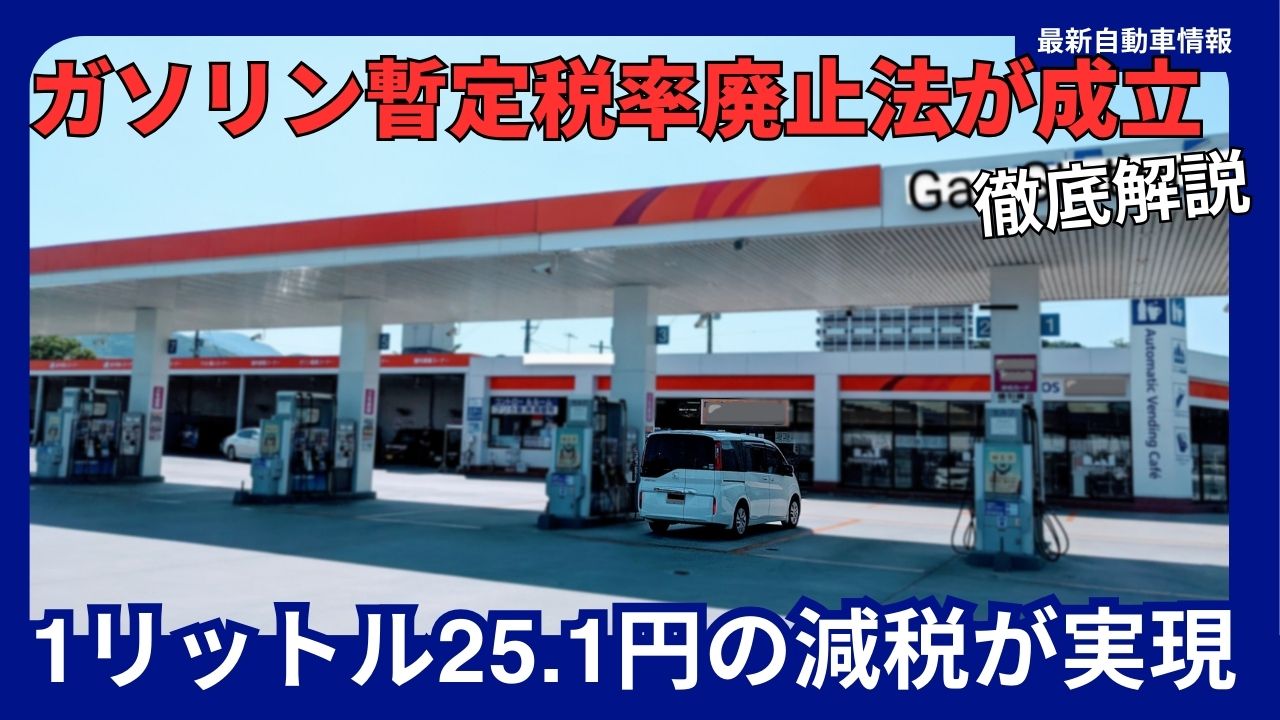2025年11月28日午前、ガソリン税に上乗せされている「旧暫定税率」を廃止する法律が参議院本会議で全会一致により可決・成立しました。これにより、1974年の導入以来50年以上続いてきた暫定税率制度が、2025年12月31日をもって廃止されることが正式に決定しました。日本経済新聞
この法案は、自民党、日本維新の会、立憲民主党、国民民主党、公明党、共産党の与野党6党が正式合意し、2025年8月に当時の野党7党が国会に提出していたガソリン減税法案を修正したものです。物価高対策として家計の負担を軽減することを目的としています。
ガソリン暫定税率とは?50年の歴史を持つ「一時的」な税制
暫定税率の成り立ちと背景
ガソリン暫定税率は、1974年に田中角栄内閣の下で導入された増税措置です。導入の直接的な理由は、1973年に発生した第一次石油危機に端を発する道路整備財源の不足でした。
当初は「第7次道路整備五か年計画(1973〜1977年度)」の財源確保のための一時的・暫定的な措置として導入されましたが、その後延長が繰り返され、実質的に恒久化されて現在まで続いてきました。
暫定税率の仕組み
ガソリン税は正式には「揮発油税」と「地方揮発油税」で構成されており、以下のような構造になっています。
【ガソリン税の内訳】
- 本則税率:28.7円/リットル
- 揮発油税:24.3円
- 地方揮発油税:4.4円
- 旧暫定税率(上乗せ分):25.1円/リットル
- 合計:53.8円/リットル
つまり、ガソリン1リットルあたりに課される税金のうち、約47%が「暫定」という名の上乗せ税だったのです。この暫定税率が2025年12月31日に廃止されることで、ガソリン税は本則税率の28.7円に戻ります。
軽油引取税も2026年4月1日に廃止
今回の法改正では、ガソリンだけでなく軽油引取税の暫定税率(17.1円/リットル)も廃止されます。ただし、軽油引取税は都道府県税であり、地方自治体への配慮から廃止時期は2026年4月1日とされました。
これにより、トラックやバス、ディーゼル車を利用する運送業界や物流業界にも大きな影響が及ぶことが予想されます。
激変緩和措置:段階的な補助金拡充で価格変動を抑制
政府の移行戦略
暫定税率の突然の廃止により、ガソリンスタンドの現場が混乱したり、価格が急激に変動したりすることを避けるため、政府は段階的な激変緩和措置を実施しています。
【補助金拡充のスケジュール】
- 2025年11月13日:10円→15円/リットルに増額
- 2025年11月27日:15円→20円/リットルに増額
- 2025年12月11日:20円→25.1円/リットルに増額(暫定税率と同額)
この措置により、消費者は12月中旬頃から実質的に暫定税率廃止と同じ水準の価格でガソリンを購入できるようになります。
補助金から減税へのシームレスな移行
12月31日に暫定税率が正式に廃止された後は、この補助金が段階的に縮小・終了する計画です。これにより、価格の急激な変動を抑えながら、補助金から減税へとスムーズに移行することが可能になります。
家計への影響:年間約1万円の負担軽減
実際にどれくらい安くなるのか?
暫定税率の廃止により、ガソリン1リットルあたり25.1円の税負担が軽減されます。さらに、ガソリン価格には消費税がかかるため、暫定税率廃止による消費税の軽減分も含めると、実質的な値下げ幅は約27〜28円/リットルになると試算されています。
【家計への影響試算】
- 月間ガソリン使用量40リットルの場合:月約1,000円の節約
- 年間使用量480リットルの場合:年間約12,000円の節約
特に車を頻繁に利用する地方在住者や、通勤で車を使う家庭にとっては、大きな負担軽減となります。
地域による恩恵の差
ただし、専門家の分析によると、ガソリン減税の恩恵には地域格差が存在します。車の利用頻度が高い地方部では恩恵が大きい一方、公共交通機関が発達した都市部では相対的に小さくなります。
例えば、鳥取県のような車社会では東京都の約5倍の恩恵を受けるという試算もあります。また、所得が高く車の利用頻度が高い層ほど、減税効果が大きくなる傾向があります。
最大の課題:1.5兆円の財源をどう確保するか
国と地方で年間1.5兆円の税収減
ガソリンと軽油の旧暫定税率廃止による税収減は、国と地方を合わせて年間約1.5兆円に達すると見込まれています。この巨額の財源をどのように確保するかが、最大の課題となっています。
【減収の内訳】
- 国の減収:約1兆円
- 地方自治体の減収:約5,000億円
特に地方自治体にとっては、道路整備や公共交通維持の重要な財源が失われることになり、深刻な影響が懸念されています。
代替財源の検討方針
成立した法律には、今後の財源確保の方針が明記されています。
【法律に記載された財源確保策】
- **「徹底した歳出の見直し等の努力」**を前提とする
- 法人税の租税特別措置の見直し
- 極めて所得が高い層への負担増
- 2025年末までに結論を得る
さらに、道路などのインフラ整備の安定財源については、今後1年程度かけて議論するとしています。
地方自治体への対応
地方自治体の減収分については、「具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得る」と記載されており、それまでの間は支障が生じないよう「適切に対応」することが盛り込まれました。
高市早苗首相は「地方に十分配慮し、必要な一般財源を確保する」と表明していますが、具体的な財源確保策はまだ明確になっていません。
環境への影響と脱炭素政策との矛盾
COP直前の「逆行策」との指摘
ガソリン減税は家計支援として評価される一方、環境政策の観点からは批判も出ています。ガソリン価格の引き下げは、燃料消費を促進し、温室効果ガスの排出増加につながる可能性があるためです。
国際的には炭素価格を引き上げて脱炭素を促進する方向にある中、日本がガソリン税を引き下げることは、COP(国連気候変動枠組み条約締約国会議)直前の逆行策と指摘する専門家もいます。
長期的なエネルギー政策との整合性
ガソリン暫定税率は、図らずも**「隠れたカーボンプライシング(炭素価格)」**として機能していた側面があります。その廃止により、電気自動車への移行インセンティブが弱まる可能性も懸念されています。
道路特定財源制度の歴史と変遷
道路特定財源制度とは
ガソリン税は、かつて道路特定財源制度の中核を担っていました。これは、自動車利用者が道路の維持・整備費を負担するという受益者負担・原因者負担の原則に基づく制度です。
1953年に創設されて以来、高度経済成長期の道路整備を支える重要な財源として機能してきました。
2009年の一般財源化
しかし、道路整備が全国に広がり、必要性の低い地域にまで高速道路建設が行われていることが問題視されるようになりました。こうした弊害を取り除くため、2009年に道路特定財源制度は廃止され、一般財源化されました。
これにより、ガソリン税の税収は道路整備に限らず、あらゆる経費に使用できるようになりました。ただし、暫定税率自体は「当分の間税率」として存続し続けていました。
2008年の「ガソリン国会」を振り返る
一ヶ月間の暫定税率失効
ガソリン暫定税率を巡っては、2008年にも大きな政治的争点となりました。当時の自民党・福田康夫内閣は暫定税率の延長を目指しましたが、参議院で多数を占める野党の強硬な反対により実現できず、暫定税率は2008年3月31日をもって一時的に失効しました。
これにより、2008年4月のガソリン価格は大幅に下落しましたが、その後の国会で再可決され、わずか一ヶ月で暫定税率が復活するという混乱が生じました。
今回との違い
今回の廃止は、当時とは異なり与野党6党が合意した上での廃止であり、政治的な対立ではなく政策判断として実施される点が大きく異なります。
各界の反応と今後の展望
全国知事会の懸念
全国知事会は2025年11月5日、ガソリン税・軽油引取税の旧暫定税率廃止に伴う地方減収分の代替として、恒久的な安定財源の確保を政府・与党に要請しました。
例えば愛知県では約300億円、福岡県では約209億円の税収減が見込まれており、地方自治体の財政運営への深刻な影響が懸念されています。
物流業界への影響
軽油の暫定税率廃止は、トラック運送業界にとって大きな朗報です。燃料費は運送コストの大きな部分を占めており、軽油価格の引き下げは物流コストの削減につながります。
ただし、廃止時期がガソリンより遅い2026年4月1日となっているため、実際の恩恵を受けるまでには時間がかかります。
今後のスケジュールと注目点
【今後の重要なスケジュール】
- 2025年12月11日:補助金が25.1円/リットルに到達
- 2025年12月31日:ガソリン暫定税率が正式に廃止
- 2025年末まで:代替財源の具体策について結論
- 2026年4月1日:軽油暫定税率が廃止
- 2026年内:道路インフラ整備の安定財源について議論
特に注目されるのは、2025年末までに示される代替財源の具体策です。法人税の租税特別措置見直しや富裕層への課税強化など、どのような財源確保策が打ち出されるのかが焦点となります。
まとめ:家計支援と財政健全性のバランスが鍵
2025年11月28日に成立したガソリン暫定税率廃止法は、半世紀ぶりの歴史的な税制改革です。物価高に苦しむ家計にとっては年間約1万円の負担軽減となる一方、国と地方で年間1.5兆円もの税収減が発生するという大きな課題を抱えています。
【この記事のポイント】
- ガソリン暫定税率(25.1円/リットル)が2025年12月31日に廃止
- 軽油暫定税率(17.1円/リットル)は2026年4月1日に廃止
- 段階的な補助金拡充により価格の激変を緩和
- 家計は年間約1万円の負担軽減が見込まれる
- 国と地方で年間約1.5兆円の税収減が発生
- 代替財源の確保が最大の課題
- 環境政策との整合性も問われる
今後、政府がどのように代替財源を確保し、地方自治体の財政を支えていくのか、また環境政策との整合性をどう図るのかが注目されます。家計支援と財政健全性、そして環境政策のバランスをいかに取るかが、この政策の成否を左右することになるでしょう。
【関連記事】