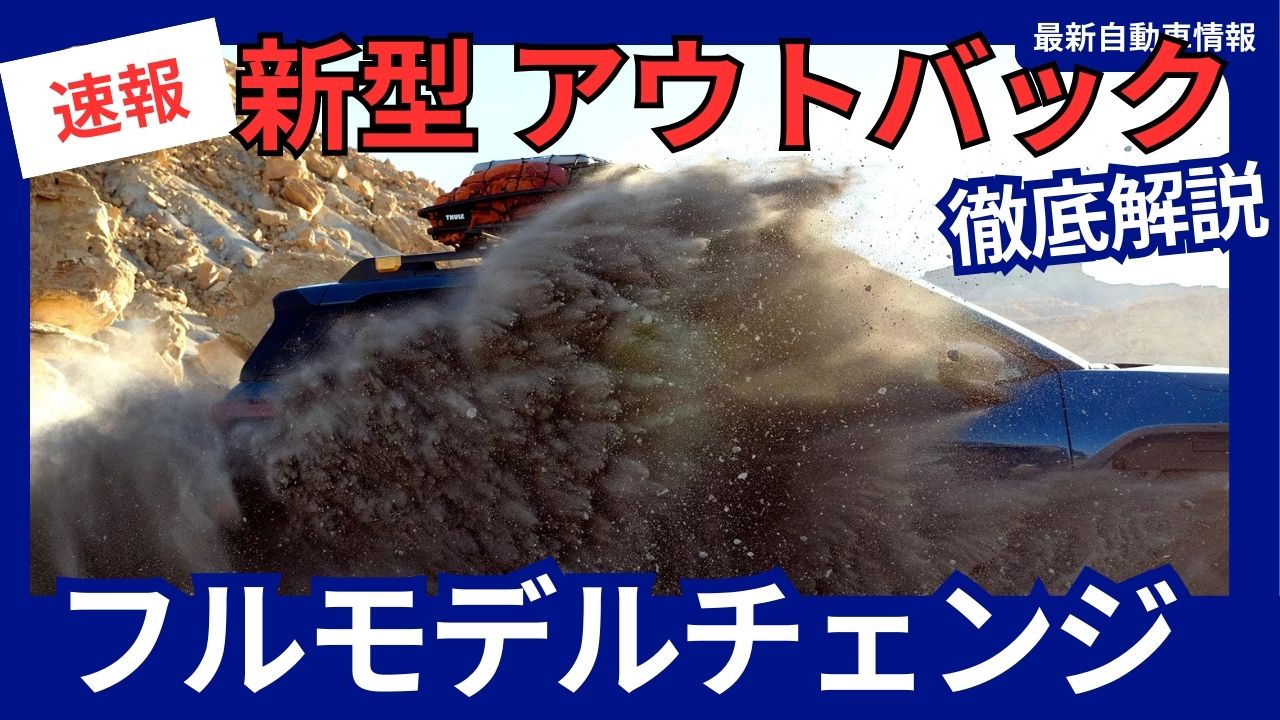自動車業界が100年に一度の大変革期を迎える中、各メーカーは電動化へのシフトを加速させています。その潮流の中で、独自の存在感を放ってきたマツダもまた、電動化戦略の新たな一手として、注目すべき新型電気自動車(EV)SUVを2025年4月10日に発表しました。中国市場向けには「EZ-60」、そしてグローバル市場、特に欧州などでは「CX-6e」として展開される予定のこのモデルは、マツダのEV戦略における重要なマイルストーンとなる可能性を秘めています。
マツダが初めて市場に投入した量産EVである「MX-30」は、観音開きのフリースタイルドアやコルク素材の内装など、マツダらしい独創性と挑戦的な試みに満ちたモデルでした。しかしながら、航続距離の短さなどが指摘され、特にEVとしての実用性においては課題も残しました。このMX-30での経験と市場からのフィードバックを踏まえ、マツダは次なる一手として、より市場の主流ニーズに応える実用性と、マツダならではのデザイン・走行性能を高次元で融合させたモデルの開発に着手しました。その結晶が、今回発表されたEZ-60/CX-6eなのです。
この新型EV SUVは、2024年4月末に開催された北京モーターショーでの正式デビューに先駆けて、その姿が公開されました。公開された画像からは、マツダのデザイン哲学「魂動(こどう)-SOUL of MOTION」を色濃く反映した、流麗かつ力強いプロポーションが見て取れます。単なる移動手段としてのEVではなく、所有する喜び、運転する楽しさを予感させる、マツダならではの生命感あふれるデザインが与えられている点は、既存のEVとは一線を画す魅力となるでしょう。特に、世界のEV市場でベンチマークとなっているテスラ・モデルYなどを検討しているユーザー層に対しても、新たな選択肢として強くアピールするポテンシャルを秘めています。
マツダ新型EV SUV「EZ-60/CX-6e」の要点まとめ
- 新型EV SUVの発表:
- マツダは、電動化戦略の新たな一手として、新型EV SUV「EZ-60/CX-6e」を発表しました。これは、MX-30に続く本格的な量産EVとなります。
- 2024年の北京モーターショーで正式に公開され、市場の主流ニーズに応える実用性とマツダらしいデザイン・走行性能の両立を目指しています。
- デザイン:
- デザインは、2023年発表のコンセプトカー「マツダ アラタ」を色濃く反映しています。
- マツダのデザイン哲学「魂動(こどう)-SOUL of MOTION」に基づき、流麗で力強く、生命感あふれるフォルムを実現しています。
- フロントはグリルレスに近いEVらしい表情ながら、力強さと知性を表現。サイドはクーペSUVのようなスポーティなシルエットが特徴です。
- ドアは実用性を考慮し、一般的なヒンジ式を採用しています。
- プラットフォームと技術:
- 基盤となるプラットフォームは、中国の自動車メーカー「長安汽車」のものを採用。同社のEVブランド「Deepal(ディーパル)」のモデルと共通です。
- この協業により、開発コストの抑制と市場への迅速な投入を目指します。
- パワートレインは、後輪駆動のシングルモーター(2種類の出力設定が予想される)が中心となる見込みです。
- バッテリー容量も2種類(68.6kWh/80kWh)が用意され、実用的な航続距離が期待されますが、SUVのためセダンモデルよりは短くなる可能性があります。
- 充電性能は最大200kW級のDC急速充電に対応すると予想され、多くの欧州メーカーと同等レベルです。
- レンジエクステンダー技術の採用は見送られ、純粋なEVとして展開される可能性が高いです(既存PHEVとの棲み分け)。
- 長安汽車との協業は、ソフトウェアやコネクティビティ分野でのメリットも期待される一方、マツダ独自の「人馬一体」の走りをどこまで実現できるかが注目点です。
- 市場展開:
- 最初の投入市場は中国(EZ-60として)です。
- 欧州市場には「CX-6e」として、2026年までの導入がほぼ確実視されています(兄弟車のセダン「6e」の先行導入予定あり)。
- 米国市場への導入は、中国生産に伴う輸入関税やEV税額控除(IRA)の対象外となる可能性が高いため、当面は見送られる見込みです。
- マツダの戦略における位置づけ:
- EZ-60/CX-6eは、マツダの「マルチソリューション戦略」を維持しつつ、EVラインナップを強化する重要なモデルです。
- 長安汽車との協業は、競争の激しいEV市場で効率的に製品を投入するための現実的な戦略的判断と言えます。
- このモデルの成功は、マツダの今後の電動化戦略やブランドイメージに大きな影響を与える可能性があります。
コンセプトカー「アラタ」のDNAを受け継ぐ、洗練されたエクステリア
EZ-60/CX-6eのデザインは、2023年に発表されたコンセプトカー「マツダ アラタ(MAZDA ARATA)」のデザイン要素を色濃く受け継いでいます。

アラタは、マツダが提案する次世代の電動SUVの方向性を示すスタディモデルであり、その市販バージョンとしてEZ-60/CX-6eは誕生しました。コンセプトカーの持つ先進性とエモーショナルな魅力を維持しつつ、量産モデルとしての現実的な要件を満たすべく、細部にわたるリファインが施されています。



フロントフェイスは、近年のマツダ車に共通する、シグネチャーウィングを廃した新たなデザイン言語を採用しています。EVならではの冷却要件の低さを活かし、グリルレスに近いソリッドな表情を持たせつつ、立体的な造形と繊細な光の表現によって、力強さと知性を両立させています。薄くシャープなヘッドランプユニットは、先進性を強調するとともに、生命感のある眼差しを表現しているかのようです。この表情豊かなフロントマスクは、競合ひしめくEV SUV市場において、EZ-60/CX-6eに明確な個性と存在感を与えています。

サイドビューに目を向けると、魂動デザインの特徴である、生命感のあるダイナミックな動きを表現したキャラクターラインが見て取れます。特に、フロントフェンダーからリアへと駆け上がるような力強いショルダーラインと、それに対比するように滑らかに絞り込まれたキャビン後部の造形は、SUVでありながらクーペのような流麗さとスポーティネスを感じさせます。コンセプトカーではカメラ式のデジタルアウターミラーが採用されていましたが、市販モデルでは法規対応やコストの観点から、地域によっては従来型のミラーも設定される可能性があります。しかし、コンセプトカーで示されたフレームレスのドアガラスや、劇的に傾斜したDピラーが生み出すクーペライクなシルエットは、市販モデルにもしっかりと受け継がれており、スタイリッシュな印象を際立たせています。

リアデザインもまた、マツダらしい引き締まったスポーティな造形となっています。左右のコンビネーションランプを繋ぐ水平基調のデザインは、ワイド感と安定感を演出し、特徴的な円形モチーフを内包したランプグラフィックは、マツダブランドのアイデンティティを主張します。リアゲートの形状やバンパーのデザインも、空力性能とデザイン性を両立させるべく、細部まで計算されています。

MX-30ではユニークなフリースタイルドアが採用されましたが、EZ-60/CX-6eではより実用性を重視し、従来型のヒンジ式ドアが採用されています。これにより、後席へのアクセス性や日常的な使い勝手が向上しており、ファミリーユースなども含めた幅広いユーザー層に受け入れられやすい設計となっています。

全体として、EZ-60/CX-6eのデザインは、マツダが長年培ってきた魂動デザインの哲学を、EVという新たな時代に合わせて昇華させたものと言えるでしょう。単に未来的であるだけでなく、クルマ本来の持つ美しさや生命感を追求したそのフォルムは、多くの人々の感性に訴えかける力を持っています。

中国・長安汽車との協業:新たなプラットフォームと電動化技術
EZ-60/CX-6eの開発において特筆すべき点は、その基盤となるプラットフォームに、中国の大手自動車メーカーである長安汽車(Changan Automobile)のアーキテクチャを採用していることです。これは、マツダの電動化戦略における新たなアプローチであり、開発リソースの効率化と、競争の激しい中国市場およびグローバル市場への迅速な製品投入を可能にするための戦略的な判断と言えます。

この協業は、EZ-60/CX-6e SUVだけでなく、同時に発表されたセダンモデル「EZ-6」(海外市場では「6e」)にも適用されています。つまり、マツダの新たな中核を担うであろう2つのEVモデルが、長安汽車のプラットフォームをベースに開発されているのです。具体的には、長安汽車の電動ブランド「Deepal(ディーパル)」のモデル、特に「S7」(SUV、旧称S07)や「SL03」(セダン)と共通の基盤技術が用いられていると考えられます。Deepal S7は、既に中国市場でテスラ・モデルYの有力なライバルとして認知されており、2025年末までには欧州市場への投入も計画されている注目モデルです。この実績あるプラットフォームを活用することで、マツダは開発期間の短縮とコスト削減を実現しつつ、一定の性能と品質を確保することが可能になります。

EZ-60/CX-6eの具体的なパワートレイン構成やバッテリー容量、航続距離といったスペックの詳細は、北京モーターショーでの正式発表を待つ必要がありますが、先行して情報が公開されている兄弟車、EZ-6/6eセダンのスペックから、ある程度の類推が可能です。欧州市場向けの6eセダンでは、主に2種類のパワートレインが用意されると見られています。どちらも後輪を駆動するシングルモーター方式で、エントリーモデルが約241馬力(180kW / 244PS)、上位モデルが約255馬力(190kW / 258PS)の最高出力を発生すると予想されます。
バッテリーに関しては、68.6kWhと80kWhという2種類の容量が設定される可能性が高いです。これにより、WLTPモードでの航続距離は、セダンで約483km(300マイル)から555km(345マイル)程度が見込まれています。ただし、SUVであるEZ-60/CX-6eは、セダンと比較して車両重量が重く、前面投影面積も大きくなるため、空気抵抗も増加します。これらの要因から、同じバッテリー容量を搭載した場合でも、航続距離はセダンよりも若干短くなることが予想されます。それでも、MX-30と比較すれば大幅な改善であり、日常的な使用から長距離移動まで、より安心して使える実用的な航続性能が確保されることは間違いないでしょう。
充電性能に関しては、Deepalが採用するプラットフォームは、最大で200kW程度のDC急速充電に対応しているとみられます。これは、ヒュンダイ・キアグループが採用するE-GMPプラットフォームの800Vシステム(最大350kW級)と比較するとやや見劣りするものの、フォルクスワーゲンやボルボなど、多くの欧州メーカーの現行EVと同等レベルの性能であり、実用上は十分な速度と言えます。一般的な急速充電器を利用した場合、バッテリー残量の大半を30分程度で回復させることが可能でしょう。
また、長安汽車のプラットフォームは、設計の柔軟性が高いことも特徴の一つです。中国市場向けのDeepal S7には、純粋なEVモデルに加えて、発電用の1.5リッターガソリンエンジンを搭載したレンジエクステンダーEV(EREV)もラインナップされています。このレンジエクステンダー技術は、バッテリー切れの不安を解消し、充電インフラが未整備な地域でも長距離移動を可能にするというメリットがあります。しかし、マツダは既に「CX-60」や「CX-80」といったモデルで、自社開発のプラグインハイブリッド(PHEV)システムを展開しています。これらのPHEVモデルは、外部充電によるEV走行と、エンジンによる長距離走行を両立しており、ある意味でレンジエクステンダーと同様の役割を果たすことができます。そのため、マツダがCX-6eに長安汽車のレンジエクステンダー技術をそのまま流用する可能性は低いと考えられます。マツダとしては、既存のPHEVラインナップとの棲み分けや、ブランドイメージの維持といった観点からも、CX-6eは純粋なEVとして展開することを選択する可能性が高いでしょう。

一方で、長安汽車との協業は、ソフトウェアやコネクティビティといった領域においてもメリットをもたらす可能性があります。近年の自動車開発において、ソフトウェアの重要性はますます高まっています。インフォテインメントシステム、運転支援システム(ADAS)、OTA(Over-The-Air)によるソフトウェアアップデート機能など、ユーザー体験を左右する要素において、中国メーカーは急速な進化を遂げています。長安汽車との提携を通じて、マツダはこれらの先進的なソフトウェア技術やコネクテッドサービスを、比較的低いコストで自社モデルに導入できる可能性があります。これにより、EZ-60/CX-6eの商品力をさらに高めることができるでしょう。
ただし、他社プラットフォームの採用は、マツダ独自の「人馬一体」を追求する走り味の実現において、一定の制約となる可能性も否定できません。マツダはこれまで、シャシー、サスペンション、ステアリング、パワートレインなどを統合的に制御する「スカイアクティブ ビークル アーキテクチャ」によって、意のままの走りを追求してきました。長安汽車のプラットフォームをベースに、どこまでマツダらしいドライビングフィールを注入できるのか、そのチューニングの手腕が問われることになります。マツダのエンジニアたちが、この新たな基盤の上で、どのような走りの価値を提供してくれるのか、大いに注目されるところです。
グローバル市場への展開戦略:欧州を主戦場に、米国は見送りか
マツダEZ-60/CX-6eの市場展開戦略は、地域によって異なるアプローチが取られる見込みです。まず、最初の主戦場となるのは、開発パートナーである長安汽車のお膝元、中国市場です。世界最大の自動車市場であり、かつEVの普及が急速に進んでいる中国において、EZ-60はマツダのブランドイメージ向上と販売拡大に貢献することが期待されます。競争が激化する中国EV市場において、スタイリッシュなデザインとマツダブランドへの信頼性を武器に、一定のシェアを獲得することを目指します。
そして、グローバル市場においては、特に欧州市場が重要なターゲットとなります。欧州連合(EU)は、厳しい環境規制と積極的なEV普及策を背景に、世界有数のEV市場へと成長しています。マツダはこれまでも欧州市場を重視しており、デザインや走行性能にこだわる欧州の消費者の嗜好に合ったモデルを投入してきました。現時点で、マツダはCX-6eの欧州導入を正式に発表してはいませんが、その可能性は極めて高いと考えられます。その根拠として、まず兄弟車である6eセダン(中国名:EZ-6)が、2024年後半にも欧州市場で発売されることが既に示唆されている点が挙げられます。セダンとSUVは共通のプラットフォームと主要コンポーネントを使用しているため、SUVモデルであるCX-6eも、セダンに続いて欧州市場に投入されると考えるのが自然です。
さらに、欧州ではSUVの人気が依然として高く、EVにおいてもSUVセグメントは販売の主力となっています。テスラ・モデルYをはじめ、フォルクスワーゲンID.4、シュコダ・エンヤック、ヒュンダイ・アイオニック5、キアEV6など、多くの競合モデルがひしめく激戦区ですが、それだけ市場規模も大きいことを意味します。マツダが欧州でのEV戦略を本格化させる上で、競争力のある電動SUVの投入は不可欠と言えるでしょう。これらの状況を考慮すると、CX-6eが2026年までには欧州市場で発売されることは、ほぼ確実視されています。もし導入が見送られるようなことがあれば、それはマツダの欧州戦略における大きな後退を意味するため、考えにくいシナリオです。欧州市場におけるCX-6eの成功は、マツダのグローバルな電動化戦略全体の成否を左右する重要な要素となるでしょう。
一方で、期待される北米市場、特に米国への導入については、残念ながら現時点では見送られる公算が高いと見られています。その最大の理由は、EZ-60/CX-6eが中国で生産されることにあります。近年、米国では中国製品に対する輸入関税が高く設定されており、特に自動車に関しては、中国からの輸入車に対する障壁が高まっています。さらに、米国のバイデン政権が導入したインフレ抑制法(Inflation Reduction Act: IRA)に基づくEV税額控除制度では、車両の最終組立地が北米(米国、カナダ、メキシコ)であることが要件の一つとなっています。また、バッテリーに使用される重要鉱物や部品の調達先に関する厳しい要件も設けられており、中国で生産され、中国製のバッテリーコンポーネントを多く使用する可能性のあるCX-6eは、この税額控除の対象外となる可能性が極めて高いのです。
最大7,500ドルにもなる税額控除が受けられないとなれば、価格競争力において著しく不利になります。テスラやGM、フォードといった米国メーカーはもちろん、北米でEV生産を行うヒュンダイ・キアやフォルクスワーゲンなどの競合に対して、厳しい戦いを強いられることになります。こうした輸入障壁や税制上の不利を考慮すると、マツダがCX-6eを米国市場に導入するメリットは小さいと判断される可能性が高いのです。当面の間、CX-6eは、EVシフトが先行し、かつ中国生産車に対する障壁が比較的低い中国市場と欧州市場を中心に展開されることになりそうです。米国のマツダファンにとっては残念なニュースかもしれませんが、これが現在の地政学的な状況と各国の政策を反映した、現実的な判断と言えるでしょう。
将来的には、メキシコなど北米地域での生産や、IRAの要件を満たす形でのバッテリーサプライチェーンの再構築などが実現すれば、米国市場への導入の道が開ける可能性も残されていますが、それはまだ先の話となりそうです。
マツダの電動化戦略におけるCX-6eの位置づけと今後の展望

マツダEZ-60/CX-6eの登場は、マツダがこれまで推進してきた「マルチソリューション戦略」を継続しつつ、電動化への取り組みを新たな段階へと進めることを示すものです。マルチソリューション戦略とは、地域ごとのエネルギー事情やインフラ整備状況、顧客ニーズの多様性に対応するため、高効率な内燃機関(SKYACTIV-X、SKYACTIV-G、SKYACTIV-D)、ハイブリッド(HEV)、プラグインハイブリッド(PHEV)、そして電気自動車(EV)といった、様々なパワートレインの選択肢を提供し続けるという考え方です。

この戦略に基づき、マツダはラージ商品群としてCX-60、CX-70、CX-80、CX-90といったモデルを市場に投入し、直列6気筒エンジンやPHEVといった新たなパワートレインを導入してきました。一方で、カーボンニュートラル実現に向けた長期的な目標達成のためには、EVラインナップの拡充も急務となっています。MX-30に続くEVとして登場するEZ-60/CX-6eとEZ-6/6eは、このEVラインナップの中核を担うモデルとして位置づけられます。
特に、長安汽車との協業という新たな手法を取り入れた点は、マツダの戦略における柔軟性と現実的な判断を示唆しています。EV開発には莫大な投資が必要であり、特にバッテリー技術やソフトウェア開発においては、先行するメーカーや巨大な資本力を持つ中国メーカーとの競争が激化しています。マツダのような比較的規模の小さいメーカーが、全ての領域で単独開発を進めることは容易ではありません。そこで、実績のある他社のプラットフォームや技術を活用することで、開発コストと時間を抑制し、競争力のあるEVを迅速に市場投入するという判断は、理に適った戦略と言えるでしょう。

この協業は、マツダにとってリスクと機会の両面を持ち合わせています。リスクとしては、前述の通り、マツダ独自の走り味やブランドイメージの維持が課題となる点、そして特定のパートナーへの依存度が高まる可能性などが挙げられます。一方で、機会としては、開発リソースをマツダが得意とするデザインや走行性能のチューニング、そして将来の独自技術開発に集中できる点、そして急速に進化する中国の電動化技術や市場動向へのアクセスが容易になる点などが考えられます。
今後、マツダはEZ-60/CX-6eとEZ-6/6eの市場での評価を見極めながら、さらなるEVラインナップの拡充を進めていくと考えられます。将来的には、トヨタ自動車との協業関係を活用したEV開発や、マツダ独自のEV専用プラットフォームの開発なども視野に入れている可能性があります。また、マツダが長年研究開発を続けてきたロータリーエンジンを発電機として使用する、独自のレンジエクステンダーEV技術についても、今後の展開が注目されます。(MX-30 R-EVとして既に欧州などで展開されているが、より大型のモデルへの展開可能性も残る)
編集部から一言
EZ-60/CX-6eは、マツダにとって電動化時代の本格的な幕開けを告げるモデルとなるかもしれません。MX-30での挑戦を経て、より市場のニーズを見据え、現実的なアプローチで開発されたこの新型EV SUVが、世界中のドライバーからどのように受け入れられるのか。その成否は、今後のマツダのブランド価値と企業としての持続可能性を占う上で、極めて重要な意味を持つことになるでしょう。洗練された魂動デザイン、長安汽車との協業による新たな技術基盤、そして地域特性に合わせた市場戦略。これらが組み合わさったEZ-60/CX-6eの挑戦が、マツダの電動化戦略を成功へと導くことを期待したいところです。今後の詳細発表と市場での反響に、引き続き注目が集まります。